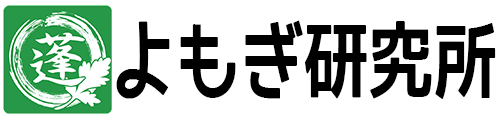食物繊維とは
食物繊維とは、食べ物の中に含まれる人の消化酵素で分解されない物質の事を指します。
水に溶ける水溶性食物繊維(SDF)と溶けにくい不溶性食物繊維(IDF)がありますが、共通して消化酵素で
分解されないので、エネルギーとして吸収する事は出来ませんが、小腸を通過して大腸まで達する事が出来ます。
消化ができないので役に立たないものだとされてきた時期もあった成分ですが、研究が進み
有用性がわかってきた現代においては、第6の栄養素とも言われるようになりました。
そんな食物繊維の効果について、大腸での効果も併せて解説します。
肥満防止
水溶性食物繊維は、胃で膨潤することで食塊を大きくし、粘性を上げ、胃の内部での滞在時間を延ばし、満腹感を与えてくれます。
不溶性食物繊維は、食べ物の咀嚼回数を増加させ、唾液や胃液の分泌を促して食塊を大きくすることによって同様に効果を与えてくれます。

コレステロール上昇抑止
食物繊維は食物のコレステロールの吸収を抑制してくれ、更にコレステロールの異化・代謝・排泄の促進、胆汁酸の回腸からの再吸収を阻害する事による代謝・排泄の促進などがされる為効果があります。(水溶性食物繊維の方が効果的です。)

血糖値上昇抑制
水溶性食物繊維は体内で高い粘性を有するため、十二指腸や空腸の内容物の拡散速度と移動速度を遅くし、グルコースの吸収を緩慢にして血糖値の上昇を抑えます。

大腸がんの発生抑制
不溶性食物繊維は、結腸や直腸で便容積を増大させ、排便を促進します。そして、発がん性物質の腸内での濃度を下げ、発がん性物質が腸管と接触する時間を短くします。
水溶性食物繊維は、腸内で発酵して短鎖脂肪酸や乳酸を生成します。それによって、腸内を弱酸性に保つことによって腸内環境を改善し、腸内細菌による二次胆汁酸やアミノ酸などの発がん性物質の産生を抑えます。

ダイオキシン類の排出
ダイオキシン類を吸着して一緒に排泄する効果があるため、通常より体内からの排出速度を2~4倍に高めることが出来ます。この事から、ダイオキシン類の健康に対する影響を防ぐことが出来ると示唆されています。