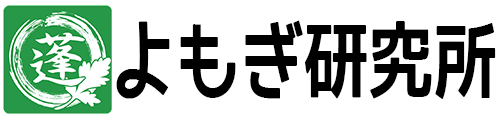ABOUT
よもぎ研究所について
よもぎ研究所へご訪問頂きありがとうございます!
当ホームページでは身近な薬草であるよもぎについて、歴史や効能・活用法を調べて
情報発信を行っているWebサイトになります!
CONTENTS

蓬(よもぎ)とは?
身近な植物であるよもぎについての説明や、名前の由来・歴史・逸話などをまとめてみました!

よもぎの効能
飲んでも、付けても、浸かっても、嗅いでも、燃やしても良し!の五拍子揃っている薬草と言われるよもぎの持つ幅広い効能とは!?

よもぎの成分
別名『ハーブの女王』とも呼ばれるよもぎですが、そのよもぎの持つ栄養面から見た時の成分について、色々まとめてみました!

よもぎ活用術
よもぎを生活に取り入れたいけどどうすれば…とお悩みの方に、すぐ出来そうなものから最近流行な活用法まで様々な活用法をまとめました!
※現在移行作業中です…
※現在移行作業中です…
SPECIAL
崇城大学薬学部教授
村上 光太郎先生講演会
TKU(熊本テレビ)の情報番組「ぴゅあピュア」で水曜日のゲストコメンテーターを務めるなど気取らない気さくなキャラクターが人気の村上光太郎先生の講演会の様子をまとめました!


卵を進化させる発酵よもぎの力!
養鶏場を経営されている松本さん。卵の生産者である彼の娘は何と卵アレルギーで生まれてきました。ショックを受けながらも、何とか自分の作った卵を食べさせることが出来ないかと試行錯誤していたところに、発酵よもぎと出会った松本さんの体験談をまとめました!